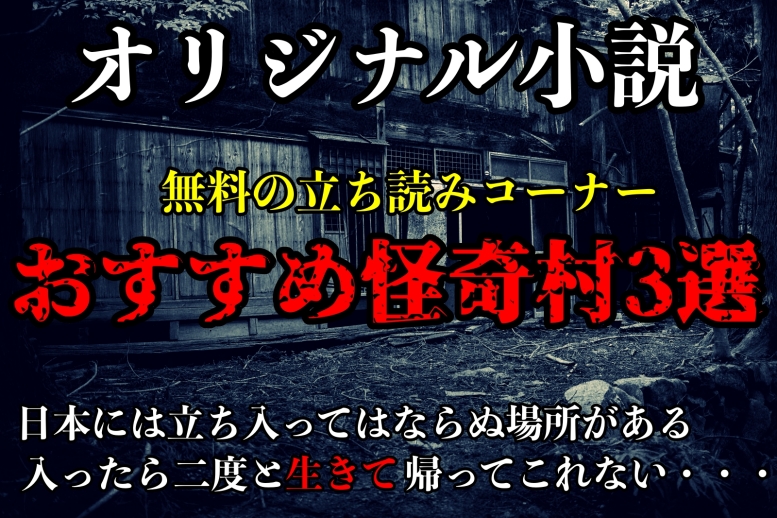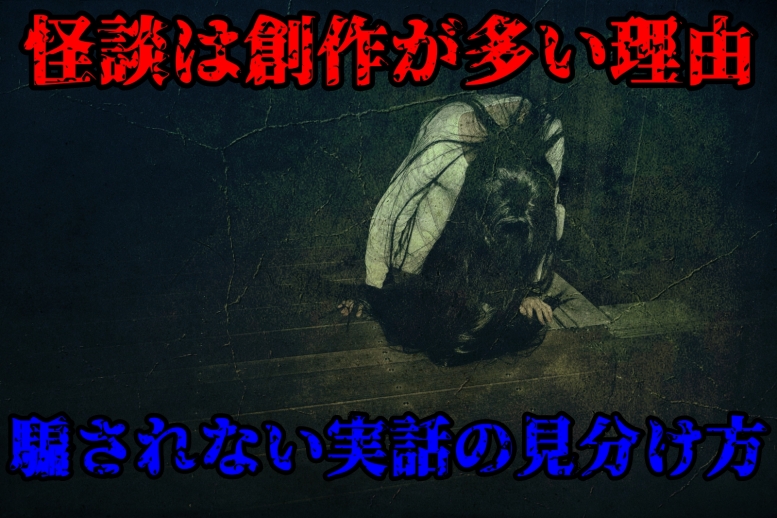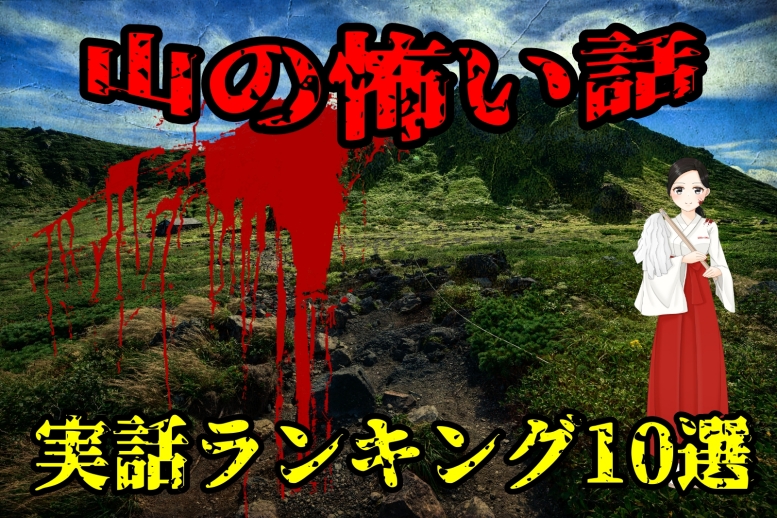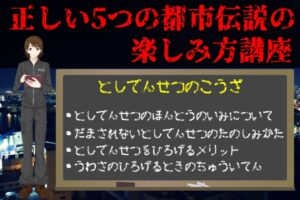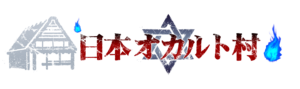御薬袋ノ村の呪い 作者:ななおしん 36歳
山梨と東京の県境あたり、奥多摩湖をさらに山の奥へと踏み入ったエリアは、かつて「御薬袋ノ村(みないのむら)」と呼ばれていた場所だった、と言われている。
健康自慢のご長寿が住む家が立ち並び、医者や薬を必要としなかったほどである、と噂されたことから、この名前がつけられたとされていた。しかし、現在の地図ではその所在を確認することはできない。
そればかりか、観光などで奥多摩エリアがさかんに取り上げられるようになった昨今、この村の名前がメディアに登場することすら皆無である。
御薬袋ノ村は、地図からも人々の記憶からも失われてしまっていた。
ある年の、夏の終わりの頃合いのことである。
「ねえ、ちょっと気になってるんだけどさ。」
大学生のカップルの秋矢(しゅうや)と心春(こはる)は、夏の思い出作りに訪れた奥多摩で、三泊四日の旅行の日程を丁度終えたところであった。
ハンドルを握る秋矢も、助手席の深春も、普段は都心近くの大学に通い、大学付近の学生アパートとバイト先と大学とを、行ったり来たりするばかりの生活を送っている。
夏休み、ふたりの予定を合わせて訪れた奥多摩の大自然は、やや刺激に欠けるものではあったが、充分な癒しとリフレッシュを得られる環境であった。だが、その帰り道のこと。
「何だよ。」
「車、ちゃんと東京に向かってる?さっきから、どんどん山の奥に入り込んでる気がするんだけど?」
深春の言葉に、へらへらと秋矢は頷いてみせた。
「あー、やっぱりわかっちゃった?実はさっき、話に夢中になってて、曲がるとこ間違えたみたいでさあ。」
「はあ?!」
翌日、バイトの予定を入れていた深春は、秋矢の発言にきりきりと眉を吊り上げた。
「呑気なこと言ってる場合じゃないじゃない!どうすんのよ!」
「待て待て、落ち着けって。とりあえず舗装された道路が続いているし、この道幅じゃあ引き返すこともできないよ。たぶん、このまま進んでれば指示標識が出てくるだろ、そのうち。そうしたらそれを頼りに、東京方面を目指せば、」
「もう、何よその意味わかんないポジティブ思考は!標識どころか、どんどん山が深く、きゃあっ!」
突然、車ががくんと大きく揺れた。舗装されていない道に入ってしまったため、車が大きく揺れたのである。
しゃべっていた深春は、危うく舌を噛みかけた。
「うおっ、なんだこの道、すごいな。」
「ちょっと、舗装されてない道に入っちゃったわよ、これじゃあいよいよ標識なんて言ってられなくない?」
深春の言葉に、流石の秋矢も「これはヤバいかもしれん。」と思い始めた。が、そのとき。
「深春、見てみろよ。」
車を止めた秋矢が、窓の外を顎で示した。
そこには、古びたドラム缶がぽつんと、不自然に立てられている。
「何あれ?何か書いてある?」
「カタカナの……ミナイ、かな。何かの案内みたいに見えないか?」
「見えなくもないけれど……何、『ミナイ』って。」
「さあな。でも、あんなものが置いてあるってことは、この先に何か施設があるってことじゃないか?民宿とか、そういうやつ。」
「こんなガタガタ道の先に?」
深春は「そうは思えないんだけど」という眼差しで、じっと秋矢を見た。
が、良くも悪くも楽天的な秋矢は、あのドラム缶を案内看板のようなものと信じて疑っていないようだった。
「どうせ戻れないんだし、行ってみてもいいんじゃね?」
何ならもう一泊してもいいしな!と呑気に言いながら、秋矢はアクセル踏み込んでしまった。
事実、道幅は車一台分ほどしかなく、Uターンもできなければバックで進むことも難しい状況とは言えた。
(嫌な予感が、するんだけどな。)せめて開けた場所にでも出られれば、引き返すこともできるようになるだろう。
深春はそう思おうとしたが、何となく胸騒ぎがしてならなかった。
そのままどのくらい走行しただろうか。
深春の願いが通じたのか、車を切り返せそうな開けた場所に辿りついた。
「ねえ、引き返そうよ。早く帰らないと都内に戻るの遅くなっちゃう。私明日バイトだし。」
しかし、先ほどの胸騒ぎがより激しさを増すばかりの深春は、一刻も早くここを立ち去りたいという気持ちでいっぱいだった。
秋矢を促し、車を出させようとしたのだが、秋矢は。
「おい待て、見ろよ深春!すっげえ、今にも崩れそうな家があるぜ!廃墟だ!」
俺、廃墟探索してみたかったんだよな!と興奮気味に言いながら、秋矢は車から降りてしまった。
彼のいう通り、車を止めた場所からそう遠くない位置に、複数の掘っ立て小屋の跡のようなものが見える。
山が深すぎるせいか、時間のわりに薄暗く見える場所で、それらの建物跡は何とも不気味に見えた。
「バカ言ってないで、帰ろうよ!何かここイヤなの!」
「何怖がってんだよ、平気じゃんこんなの。すげー、廃村跡ってヤツ?こんなとこに村なんてあったんだな。」
半泣きの深春に構わず、秋矢はどんどん進んでしまう。
吹けば飛びそうな掘っ立て小屋風の廃墟を覗きながら、彼は奥へ奥へと歩いていった。
「私は行かないからね!」
という、深春の声を背中で聞き流しながら、ある廃墟の中を秋矢が覗きこんだ、そのときだった。
ぱきり。
何か、踏むような音がした。明らかに人の足音のようにも聞こえる。
いや、音だけではない。先ほどまでなかったはずの気配が、四方八方から押し包むように秋矢の周りに生じて、取り囲んできているのを感じた。
「だ、誰かいるんですかー!」
こんな状態の村に、住んでいる人間などいるはずがない、と。
頭ではわかっていたが、そう叫ばずにはいられなかった。
「あのー、道を教えていただきたいんですが—!」
必死に声を張り上げる秋矢の目に、何か動く影のようなものが見えた。
「あ!あのー……」
そちらに顔を向けた瞬間、秋矢は自分が入ってはならない場所に踏み込んだことにやっと気が付いた。
そこにいたのは、ぼろぼろの着物のようなものを辛うじて身に付けた、骨と皮ばかりの老人だったからである。
痩せこけすぎていて、もはや性別もわからない。
「ひっ!」
引きつったような声を上げた秋矢を取り囲んでいたのは、同様の姿をした老人の群れであった。
まるでミイラが動いているようなその姿は、生きているものだなどとは到底思えなかった。
「うわあああああ!」
弾かれたように秋矢は走り出した。前方に、佇んでいる深春の姿が見える。
一目散にそこまで走って、秋矢は深春の手を握りしめた。
「逃げるぞ!ここやべえところだった!」
「……うん、知ってる。」
「へ?」
か細い声で言う深春の顔は紙のように白い。
虚ろな視線を秋矢に向けた深春は、奇妙なことを口走り始めた。
「秋矢。私のこと、見捨てないよね?ちゃんと連れて行ってくれるよね?」
「お、おい、何だよ、どうしたんだ?」
問いかける秋矢の顔から、深春の視線が外れ、足の方へと移動する。
つられてそちらを見た秋矢は、喉の奥底から絶叫し、深春の手をふりほどいて、走り出した。
「置いて行かないでええええ!」
悲痛な深春の悲鳴から顔を背け、秋矢は車を発進させた。
秋矢は見てしまったのだ。深春の両足をがっしりと掴んでいた、骨のような細い腕を。
その後、車を走らせ続けた秋矢は何とか東京へと帰りついたが、深春はそれきり行方不明となっている。
そして秋矢も、「深春が呼んでいるんだ。」という言葉を残して失踪してしまった。
彼らが踏み込んだのが御薬袋ノ村であることを、知るものは誰もいない。
このストーリーにした理由
オリジナル小説の怖い集落シリーズとして3選ほど、ご紹介しましたが読んで少しでも日本には本当にヤバイ村があるんだと物語の中で感じられたらと思います。

最後に
日本オカルト村でご紹介している3選のオリジナル小説として公開している怖い集落の話を最後まで読んで頂けましたでしょうか?
もしかすると、あなたも実際にストーリーの中に引きずり込まれることで怪奇村に迷いホラー映画のような普通ではあり得ない経験が出来るかもしれませんね。
他にも、
- 怪談
- 都市伝説
- 未確認生物
- 宇宙人
などのオリジナル小説も公開しているので、機会がありましたら合わせて読んでみてくださいね。